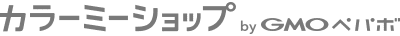陶磁器窯の物語を簡単ながらまとめています。
見る資料によって時代が少し違っていたり、内容が違っていたりで、正確な歴史を掘り起こすのは難しいと感じています。
こちらにまとめている内容は、大まかな流れと思っていただきたいことと、SLOW TIMEなりの解釈と見ていただけましたらと思います。どの陶磁器窯も、それぞれの時代を一生懸命生き、努力を重ねてきたことや、陶磁器制作にそれはそれはあふれんばかりの情熱を注いできたことを感じます。その情熱は時代を超えて今なお私たちを魅了し、心をつかんで離さないことで伺い知れます。古い時代の陶磁器は魅力にあふれています。歴史が教科書の中にではなく、体感として感じられるような目には見えない何かがあります。
初めて手にした古い1枚のお皿から、私の生活は一転しました。そのお皿の物語を手探りで探るうち、そこには作られた時の土地のエネルギーが凝縮されていて、歴史そのものだということを知ったのです。
陶磁器は、土地の名前がブランド名になっていますが、まさにその土地の粘土を使い、その土地の水で練り上げられ、その土地の木を薪として使い火を起こして焼かれます。マリーアントワネットがフランス王妃だった時にパリで作られたお皿と知って手に持つ時、そこにはまさにその時代のその場所のエネルギーがそこにあるのです。
お皿を通して歴史を振り返るようになりました。遠い国の出来事が自分に関係のない遠い過去のものではなく、今この瞬間それらを感じられるような気持ちになって、ますます陶磁器の魅力にとりつかれています。
簡単ですが、それぞれの窯の歴史をまとめています。陶磁器のブランドが必死で生き抜いてきたことがうかがい知れると思います。そうしたことを知ってお皿を見ると、胸がきゅんとします。
古いお皿は、人の手が作り出したという証が見えます。絵付けした場所にちょっと触ってしまった後が残っていたり、焼き上げた器を金具で持ち上げた際の金具の跡があったり、ちょっと絵柄がずれていたり。同じお皿でも重さが違ったり、釉薬のかけかたが少しずつ違うことで、艶かげんが1枚ずつ違ったりと、同じお皿といっても個体によって顔が違うことも魅力の一つと感じます。古いお皿には今もなお命が宿っていると感じるのです。
<あいうえお順になっています。>
フランス
エミール・ブルジョワE Bourgeois
南仏マルセイユに窯元を持ち、パリに販売拠点を持ってフランスの上流階級に愛されたブランド。1863年から1918年の50年と言うごく短い時間に高品質で上質な作品を作陶したブランド。
HB&Cie(Hyppolyte-Boulengen&Cie)
1804年にパリ近郊ショワジー・ル・ロア(Choisy le roi)で創業した窯元。ショワジー・ル・ロワ (Choisy Le Roi)でバイヤール3兄弟によって創業後、経営に参加したポリット・ブーランジェが1863年に工場のディレクターとなった後、1878年に社名を変更しH・ブーランジェ(H・Boulenger&Cie)となり最盛期を迎える。その後1920年にクレイユ・エ・モントロー(Creil et Montereau)と合併しHBCM(Hiperolyte Boulanger-Creil-Montereau)社となる。ところが1934年、労働者のストライキによってショワジー・ル・ロワの工場が閉鎖。それを機に、ここでの作陶が終わります。HBCM社として合併先のモントロー工場で作陶は続けられましたが、それも1955年に閉鎖します。
HBCM(Hiperolyte Boulanger-Creil-Montereau)
ショワジー・ル・ロワ (Choisy Le Roi)から始まり、1804年にバイヤール3兄弟によって創業。さかのぼること数年前のこと、バイヤール兄弟が磁器窯シャンティイを当時の所有者だった英国人クリストフ・ポッターから買い取り、ここでの作陶活動をしようとしていた最中の1802年。シャンティイのポッターの部下の筆頭者を始め、職人が丸ごとクレイユに転籍してしまいます。ここでの活動は難しいと判断した兄弟は、新たにショワジー・ル・ロワの地を選びます。
兄弟はここで、当時最新技術だった銅板転写の作陶を始めていきます。19世期後半には他の窯から有能な人物が集められ、窯は最盛期を迎えていきます。この時、経営に参加したイポリット・ブーランジェは1863年に工場のディレクターとなり、1878年に社名を変更しH・ブーランジェ(H・Boulenger&Cie)となっています。現在、市場で見ることのできるものは、量産ができるようになった1800年半ばから閉窯の1900年前半のものが多いようです。イポリット・ブーランジェ亡き後は彼の2人の息子が引き継ぎます。1895年にはクレイユ工場は火事によって閉鎖し、経営が困難になっていたクレイユモントローとモントロー工場を買収する形で1920年に合併、HBCM(Hiperolyte Boulanger-Creil-Montereau)社となります。その頃、メトロの壁面に使用されるタイル製造で栄えます。ところが1934年、労働者のストライキによってショワジー・ル・ロワの工場が閉鎖し、それを機にショワジー・ル・ロワでの作陶は終わります。HBCM社として合併先のモントロー工場で作陶は続けられましたが、それも1955年に閉鎖し歴史に幕を降ろします。
クレイユ・エ・モントロー(CREIL ET MONTEREAU)
クレイユとモントローのふたつの窯がひとつになって生まれた陶磁器ブランドです。
モントロー窯の創業は1749年。フランソワ・マゾワによってモントロー陶器工場が作られ、ファイアンス・フィンを発展させていきます。モントローでは陶器作りに適した白い粘度が採れたことから、クレイユにも材料を提供していました。工場ができる前の最初の窯は1719年頃に始まっています。オーナーや生産様式の変化と時代を生き抜きながら、1819年に作陶ではライバル的存在だったクレイユと合併し、クレイユ・エ・モントローとして共同制作を始めます。
一方、クレイユ窯の創業は1797年頃。英国人起業家のクリストフ・ポッターが経営に加わり、英国ではすでに発明されていた、陶器や磁器に印刷をする技術を、フランスではクレイユとジョワジー・ル・ロワが初めて導入し、窯は大きく発展します。この頃、新古典主義の作品が次々作られていきます。さらにその後新たな技術者が加わりながら発展し、オーナーの交代も経ながら(1840年から1874年までは当時合併していたオーナー名の‘Lebeuf Milliet et Cie’の刻印がされています。)1819年頃にモントロー工場を買収した形でクレイユ・エ・モントローとなります。
クレイユ・エ・モントローの作陶は優れた銅板転写で、まるでキャンパスに絵を描くような色鮮やかな陶器が特徴でした。古典主義、シノワズリ、アールヌーボーと時代とともに多くの作品を生み出してきました。フランスを代表する古窯として発展を続けてきましたが、1895年クレイユの工場が火事になり工場が閉鎖。その後もクレイユ・エ・モントローの名前で1920年まで制作を続けますが、その後ジョワジー・ル・ロワに吸収され、HBCM(H・ブーランジェー・クレイユ・モントロー)として製作が続けられました。しかし、さまざまな時代の波を乗り越えてきたものの1955年その歴史に幕を降しました。
サラン-レ-バン(SALINS-LES-BAINS)
サラン-レ-バン(SALINS-LES-BAINS)窯は、スイスとの国境に近いフランス東部のジュラ県、サラン-レ-バン(SALINS-LES-BAINS)で、1857年にファイナンスリーの製造所として創業。サラン-レ-パン(SALINS-LES-BAINS)は、古くから塩の製造でも知られる土地です。1912年にロンシャンディレクターの息子がサラン窯のディレクターとなり、洗練された作陶をしていきます。そして、そのまま所有者になり精力的に制作を続けていきますが、時代の変化の波のなかで1968年にサルグミンヌに吸収されていきます。一般向けの製造は1988年に、高級品の製造は1998年に終了しています。
サルグミンヌ(SARREGUEMINES)
1784年にニコラス・アンリ・ヤコビとそのパートナーによって、ドイツとの国境に隣接するサルグミンヌで創業。しかし経営はうまく行かず、19世期に、工場はドイツ人のポール・ウィッチシュナイザー(Paul Utzschneider)に引き継がれます。この頃の刻印はF&U (Fabry&Utzschneider)。ビジネスに長けていたポールはサルグミンヌを国際博覧会で世界に紹介し、彼の顧客はナポレオンやブルボン王朝まで到るようになります。工場の経営は順調に進み、1830年位はヴィレロイ&ボッホと資本協力し、市場を分け合うほどに成長します。そしてそれまでの薪を使っての窯焼き(薪オーブン)を蒸気運転(石炭オーブン)に設備を整え生産力も向上していきます。
ところが、1870年の普仏戦後サルグミンヌがフランス領からドイツ領に変わり、完成品をフランスに運ぶために陶器に膨大な輸出税がかかるようになったことと、サルグミンヌとしてのフランス籍を守るため、1876年にフランスブルゴーニュ地方の小さな町ディゴワンにサルグミンヌ窯を移します。
この時、ドイツ側にはUtzschneider & Cie(U&C Sarreguemines)を置き、(ドイツ側はUtzschneiderの娘婿が経営を引き継ぎ刻印はU&C(U&Cieに))、フランス側は当時すでに陶器制作をしていたディゴワン(Digoin)と合併しDigoin &Sarregueminesと、ドイツとフランスと2つの会社に分割します。
ディゴワンでは、Digoin、Sarreguemines、Digoin &Sarregueminesの3つの刻印が当初使われていましたが、その後会社名をDigoin &Sarregueminesに変更し、1881年から総称をFaienceries de Sarreguemines、Digoin et Vitry-le-Francois(ヴィトリールフランソワ) と呼ぶようになります。ディゴワンでは、ディゴワン&サルグミンヌとして100年以上に渡り、数々の陶器生産を続けてきました。
第一次大戦のドイツの敗戦によりサルグミンヌ製陶工場は再びフランス領に戻るのですが、その後は経営不振により1942年から3年間、ヴィレロイ&ボッホに経営が委託され、さらに時代の流れに逆らえず、1978年にリュネヴィル・バドンビレー・サンクレマングループに買収され、この年で食器の生産を終えています。その後はタイル製造に専念してきましたが、2002年に株主となった従業員に製造が引き継がれて、2007年に破産宣告と共にフランスを代表するディゴワン・サルグミンヌとしての古窯は200年を越える歴史の幕を降しました。
サンタマン(Saint Amand)
フランス北部、ベルギーに近いノール県のサンタマン・レゾー(Saint-Amand-les-Eaux)に、ニコラス・デムウティエールよって1705年に創業。スカーぺ川の粘土を採取、近くの森から窯のために木材を得て、完成した陶器はスカーぺ川で運ぶことができると言う陶器制作に恵まれた土地で、ファイアンス焼きを始めます。花や動物の絵柄や伝統的なブルー&ホワイトの作品が作られていきました。その後、さまざまなオーナー遍歴を繰り返し、またフランス革命によって工場が閉鎖するなど時代の波をくぐり抜けながら、1928年ムーラン・デ・ル・アマージュと名前を変更。1944年にはさらに、ムーランデルーと名前を変更すします。このとき会社は国内に5カ所展開していましたが、時代の変化に応じながら1952年からひとつずつ工場を閉鎖し、1962年には最後の工場を閉鎖してその歴史に幕を降しました。様々な遍歴を繰り返してきたためさまざまな作風と多くの刻印が存在します。現在では作陶の起源である地名の名前を取って総称してサンタマン=レゾーの陶器と呼ばれています。現在のアンティーク市場では1880年以降の作品が主となっています。
ジアン(GIEN)
正式名称は’Faiencerie de Gien’と。この名前が物語るようにGienはファイアンス焼きの陶器ブランドとなります。
ファイアンス焼きとは繊細な淡黄色の土に錫秞(しゃくゆう)をかけて焼く陶器のこと。陶器を焼く前に使われる釉薬に酸化スズを加えることで絵付に適するようになり、色鮮やかな陶器が生まれていく。
ジアンはパリの南にある緑豊かな小さな町。ロワール川が流れ、豊かな土壌と温暖な気候に恵まれたジアンで、1821年ジアン窯が創業する。創業者は英国人実業家のトマス・エドム・フルムで、英国の製陶技術を生かして始まりました。原料となる粘土はロワール川から採取し、窯の燃料となる材木は近くのオルレアンの森から得て、完成した陶器はロワール川で運搬すると言うように、窯を開くにあたってそこにすべてが揃っていた場所で始まり、現在も活動中。公式HP https://gienfrance.jp
ショワジー・ル・ロワ(CHOISY LE ROI)(Choisy Le Roi)
1804年にバイヤール3兄弟によって創業。さかのぼること数年前のこと、バイヤール兄弟が磁器窯シャンティイを当時の所有者だった英国人クリストフ・ポッターから買い取り、ここでの作陶活動をしようとしていた最中の1802年。シャンティイのポッターの部下の筆頭者を始め、職人が丸ごとクレイユに転籍してしまいます。ここでの活動は難しいと判断した兄弟は、新たにショワジー・ル・ロワの地を選びます。
兄弟はここで、当時最新技術だった銅板転写の作陶を始めていきます。19世期後半には他の窯から有能な人物が集められ、窯は最盛期を迎えていきます。この時、経営に参加したイポリット・ブーランジェは1863年に工場のディレクターとなり、1878年に社名を変更しH・ブーランジェ(H・Boulenger&Cie)となっています。現在、市場で見ることのできるものは、量産ができるようになった1800年半ばから閉窯の1900年前半のものが多いようです。イポリット・ブーランジェ亡き後は彼の2人の息子が引き継ぎます。1902年にはクレイユは火事によって工場が閉鎖し、経営が困難になっていたクレイユモントローとモントロー工場を買収する形で合併し、HBCM(Hiperolyte Boulanger-Creil-Montereau)社となります。その頃、メトロの壁面に使用されるタイル製造で栄えます。ところが1934年、労働者のストライキによってショワジー・ル・ロワ工場は閉鎖し、それを機にここでの作陶が終わります。HBCM社として合併先のモントロー工場で作陶は続けられましたが、1955年に閉鎖し歴史に幕を降ろします。
バドンヴィレ(BADONVILLER)
バドンヴィレの歴史は、フェナル一家がペクソンヌで窯を始めたところから始まります。ペクソンヌ窯はリュネヴィル、ニダーヴィレー、サンクレモン、バドンヴィレーなど著名な窯がある場所で、陶磁器作りに向いた土地でした。ペクソンヌ窯は1720年頃から始まった古窯で、1836年からニコラ・フェナルが正式オーナーとなります。ニコラ亡き後は息子と甥たちが引き継ぎFenal Frères(FF)の刻印が使われています。そこからペクソンヌは大きく成長していき、近隣の陶磁器製造の窯の職人たちもペクソンヌに移り、さらに素晴らしい作品を生み出して、ペクソンヌ フェナル兄弟(PEXONNE FENAL Freres)として成功を収めます。その後、1897年にペクソンヌ フェナル兄弟の中の一人だった甥のテオフィル・フェナル(Thèophile Fenal)は家族とうまく行かず、ペクソンヌ窯から分鎌する形でバドンヴィレーに独立し、1898年バドンヴィレ工場を作ります。これがバドンヴィレの始まりです。刻印はTF(Thèophile Fenal)となり、銅板からの写絵のような特徴的なペイントやエアブラシの装飾技法などにチャレンジし、すぐに300名の従業員を雇うまでに成長します。1905年のテオフィル亡き後は息子のエドゥワルドが引き継ぎ、すぐに従業員1000名を超えるまでに拡大していきます。アールヌーヴォーテーブル食器74ピースセットなどの大作を作るなど、バドンヴィレの栄光の時代を飾ります。1920年にエドゥワルドはリュネヴィル・サン=クレモン窯の指揮もするようになり、刻印に「KG」が刻まれます。その後第二次世界大戦後では縮小したものの、戦後はエドゥワルドの息子のジルベートが後を継ぎ、さらにヴァドンヴィレは発展していきます。1950年頃のフェナルグループの窯は、フランスの30%を占めていたそうです。1963年にはバドンヴィレ窯とリュネヴィル・サン=クレモン窯をひとつにして生産を始め(合併後の刻印はBadonvillerに統一されています)、1980年にはフェナルグループはサルグミンヌ窯とも合併し(Sarreguemines 社と合併後は刻印をLunevillーSt・Clementにしています)、生産を続けていきます。しかし1990年にバドンヴィレ窯はサン=クレモン窯のみを残して歴史に幕を降ろします。バドンヴィレーは新興窯ながら特に1900年後半のフランスで地位を確立した窯です。
ペクソンヌ(PEXONNE)
1719年、ペクソンヌにニコラス・フェナルが窯を始めます。近隣諸国との戦争が続いていた時代、金属類の不足から、ルイ14世は銀食器の使用禁止を命じたため、‘銀食器に代わるものをファイアンスで作りなさい’とロレーヌ地方の公爵がペクソンヌ村に窯を作らせたのが始まりです。1836年からニコラスが正式オーナーとなり、ニコラス亡き後は息子と甥たちが引き継ぎ(バックスタンプはFenal frères((F F))大きく成長していきます。ペクソンヌはリュネヴィル、ニダーヴィレー、サンクレモン、バドンヴィレーなど著名な窯がある場所でしたが、それらで活躍していた職人たちがペクソンヌに移ったことで、窯は大いに盛り上がります。そこで、ペクソンヌ フェナル兄弟(PEXONNE FENAL Freres)として成功を収めます。その後甥の一人のテオフィル・フェナルがバドンヴィレーに窯を開いて分窯。新しい手法を展開していくバドンヴィレーに注目が集まるようになり、次第にバドンヴィレーが優勢になっていきペクソンヌ窯は終わりを迎えることになります。
リュネヴィル(Luneville)
ロレーヌ地方のムルト・エ・モゼル県にあるリュネヴィル(古くは女神ディアーナを信仰する‘月Luna’と名前が入ったLunae-villeが土地の呼び名の始まり)で、近郊のサンクレマンで採れる粘土を元に、1728年にジャック・ジャンブレットがリュネヴィルに最初の陶器工場を設立し、リュネヴィル焼きの制作を始めます。1758年にはサンクレマンに第2工場を設立します。当初は上流階級向けの高級な食器を生産し、1749年にはロレーヌ公の領主御用達になっています。ルイ14世の時代、戦争のための資金調達のためシルバー製の食器製造が国王によって禁止されていた1700年〜1800年に、ロレーヌ公の命によってファイアンス焼きの食器の製造が始まっています。
ジャック亡き後、ドイツ出身のケラー(Kellen)ファミリーと友人ゲラン(Guerin) ファミリーが経営を引き継ぎ、刻印はLuneville K&Gとなります。
ここから貴族のための陶器から中流階級のための食器も手がけていきます。マリーアントワネットはリュネヴィルの食器を愛し、リュネヴィルの保護もしています。小トリアノンの庭に飾られていた食器は1500とも2000とも言われています。チューリップやバラなどの花々や、鳥や動物などが描かれた温かく優しい絵柄をはじめ、1800年後半にはシノワズリやアール・ヌーヴォーなどの流行のデザインも取り入れられ、フランス国内のみならず、ヨーロッパ中に輸出されるようになります。
それでも世界の変化とともに、1922年にはバドンヴィレが工場を買収し合併します。さらに1979年にはサルグミンヌと合併しています(この時の刻印はLuneville-St Clement)。
その後、1981年にリュネヴィル窯は生産を停止。サンクレマン工場は1999年に生産を停止、その歴史に幕を降すことになります。
ロンウィー(LONGWY)
北フランスロレーヌ地方のロンウィに1798年創業。シャルル・レ・ニエが古い修道院の中に作陶の窯を作ったのが始まりです。1810年のナポレオン戦争時、ドイツ軍による市内包囲によって工場は活動停止し困窮しますが、ルクセンブルクのヴィレロイ&ボッホ創始者の親戚にあたるジャン・アントワーヌ・ド・ノトームが窯を買い取り、経営を引き継ぎます。1800年半ばにはロンウィーエナメルと呼ばれるエナメル陶器の生産を始め、陶器ブランドとしてその地位を獲得。1900年には初期アールデコ陶器を制作したりと精力的に生産を続けています。
ドイツ
KPM ベルリン
正式名称は、KPMベルリン王立磁器製陶所(Konigliche Porzellan Manufaktur)。フリードリヒ大王によって1763年創業。ドイツの主要窯7つのひとつに数えられる人気ある窯。国王自らが選んだバックスタンプはブランデンブルグ選帝侯時代の紋章で、あらゆる分野に王自身が関わり指揮し、マイセンに並ぶ高品質の作品を作り上げ、250年以上の歴史を誇る。
ビレロイ&ボッホ(VILLEROY&BOCH)
1748年フランソワ・ボッホによって、フランスのロレーヌ地方に創業。その後ルクセンブルグにも工場を設立。ハプスブルグ家の援助を受け王室御用達の窯として発展する。その後1836年に陶器制作ではライバルでもあったビレロイ家と合併し、ドイツに本社を構えてビレロイ&ボッホとなる。2つの力を合わせていち早く制作の工業化を始め、マイセン、ロイヤルコペンハーゲンに並ぶ世界三大陶磁器の会社となる。
現在はメトラッハに本社を持つドイツの陶磁器会社。
イギリス
アダムズ(ADAMS)
1657年にジョン・アダムスがThe Adams familyとして家族でStaffordshireのバースレムに窯を起こしたのが始まり。代々続く陶芸づくりの家に生まれたウィリアム・アダムスもまた兄弟と同じく、家業に携わっていきます。のちにウィリアムが引き継ぎ、18世紀の初めには銅板プリント転写技術を確立し、英国らしさ溢れる食器を生み出していきます。この頃の作品はWilliam Adamsと呼ばれているようです。
17世期から始まり、代々受け継がれてきたADAMSは、英国の陶器づくりの世界でもかなり古窯です。
確立した転写技術は外部にもれないよう、二人の職人のみによって極秘で行なわれていたそうです。
ウィリアムからさらに息子たちに引き継がれて、しっかりと製造技術を守りながら先祖11代まで受け継がれてきましたが、さまざまな窯が発展していく中で、競争が激しくなっていたのだろうとも想像します。
時代の波から逆えず、1966年にウェッジウッド(Wegewood)グループに吸収されます。
そこからの作品はウエッジウッドらしい上品なムードを醸し出すようになったと感じます。
それ以前のADAMSは素朴さが漂っているように感じます。
ウェッジウッド(Wedgwood)
1759年にジョサイア・ウェッジウッドがStaffordshierに創業した英国の陶磁器メーカー。努力を重ねた開発の末生まれたエネメルを用いたクリーム色の陶器は絶賛され、1765年には「クイーンズウェア(女王の陶器、Queen's Ware)」という名称を与えられる。開発拡大とともに世界的な輸入も始まりウェッジウッドの名が世界に轟いていくが、時代の波の中で買収拡大をしながら、2015年フィンランド企業フィスカースに買収され、ロイヤルドルトン、ロイヤルアルバートと共にWWRDグループホールディングスの一員となる。
ウッド&サンズ(Wood&Sons)
1865年、Absalom Woodとその息子たちと創業。1910年に会社設立と世代交代をして多くのテーブルウエアを製造してきました。中流階級向けの老舗陶磁器メーカーとして英国中の家庭でよく目にするブランドです。銅板転写によりブルー&ホワイトで英国のカントリーサイドが描かれる作品が得意です。残念ながら時代の変化の中で1995年に閉窯しました。
エインズレイ (Aynsley)
1775年ジョン・エインズレイ によって創業。2代目の時代にティーセットに情熱が注がれ、 3代目の時代にはスポードが開発したファイン・ボーンチャイナの技術を取り入れ、高品質な製品を生み出していきます。 ヴィクトリア女王やエリザベス2世など英国王室に愛され、その地位を獲得しています。華やかな花々が描かれ、金彩を施したティーセットは今も世界中にファンを持っています。現在は80か国に輸出されている英国の古窯になっています。
エノク・ウエッジウッド(ENOCH WEDGWOOD)の始まりは1834年。タンストール(Tunstall)で活動していたユニコーン窯(Unicorn Pottery)は、Swan Bank Potteryほか2つの窯と合併吸収しながら活動を続けてきたが、1859年にはウェッジウッドの創業者のジョサイア・ウェッジウッドの遠い親戚だったエノク ・ウェッジウッドが事業を引継ぎ、Wedgwood & Coと名前を変えます。1900年にはWedgwood & Co Ltdとなり、Imperial Porcelain、Royal Stone China、Wacol Ware、Wacol Imperial, Royal Tunstallなどで陶器の製造をします。1965年にはWedgwood & Co LtdとPinnox Potteryが合併し、Enoch Wedgwood (Tunstall) Ltd となります。英国の陶器窯はフランスと同じく、吸収されながら成長し今に至っていまが、1980年にはウエッジウッド・グループに吸収されます。
ジョンソンブラザーズ(Jonson Brothers)
イギリス ストークオントレントで1883年創業の食器ブランド。オリジナルの4人の「ジョンソンブラザーズ」は、アルフレッド、フレデリック、ヘンリー、ロバート。彼らの父は、陶芸家のアルフレッド・ミーキンの娘と結婚後、陶器の生産を始めます。創業当初はホワイトグラナイト「白い花崗岩」と呼ばれる耐久性のある陶器を制作。その後、高級陶器の特徴を持ちながら、鉄石製品の耐久性を備えた「半磁器」と呼ばれる陶器を開発し、高い人気を得ます。輸出業も波に乗り成長しますが、第二次大戦で工場は停止。戦後は設備を整え再建を目指します。ジョンソンブラザーズは、英国経済への貢献により、クイーンエリザベス2世とクイーンマザーからロイヤルワラントを受賞しています。1890年代から1960年代にかけて、米国に多く輸出された食器を製造した最も成功したスタッフォードシャー陶器として地位を確立。また衛生設備がなかった時代に、バスルームセラミックの重要なメーカーとして開発に力を注ぎ、衛生設備を整えることにも貢献しています。しかしながらこうした2度の受賞も、1960年半ばには競争の激化が始まり、時代の波の中でウェッジウッドグループに吸収されます。そこから1968年から2015年まではウェッジウッドでの製陶活動があったものの、2015年にウェッジウッドグループがフィスカースに買収された後、ジョンソンブラザーズは132年間の歴史の幕を降します。
スポード(Spord)
1770年陶芸家ジョサイア・スポードがストーク・オン・トレントに陶芸工業を開設。実際にはジョサイア・スポード幼少期から小さな陶器工房で丁稚奉公を始め、16歳の時、陶器の世界に身を埋める覚悟をします。就職した陶器工房でのちのウエッジウッドの創始者のジョサイア・ウェッジウッドが共同経営者として加わり、彼からも影響を受けていきます。いくつかの窯を歩きながら修行を重ね、1770年ごろから自らが焼いた陶器にSpodeの名前を入れるようになります。そこからSpode窯は1770年創業と呼ばれるようになっています。研究熱心なジョサイア・スポードは銅板転写技術による絵付け技術を開発し、さらにボーンチャイナを完成させるなど開発に力を注ぎながら、陶器と磁器の両方の長所を持つストーンウエアを完成させます。これにより1806年ジョージ4世より英国王室御用達としてロイヤル・ウォラントの称号を授かります。1833年には買収によってオーナーが変わリ、販路拡大に成功して英国を代表するブランドのひとつとなります。1843年位はボーンチャイナを超えるファインチャイナを完成させます。1847年に長年ともに共同経営をしてきたコープランド家がW・T・コープランドとして正式オーナーとなります。1863年にはコープランドの4人の息子が加わり、W・T・Copeland & sonsと改名。1970年にはコープラントが窯の権利を売却したことで、窯の名前はSpode.Ltdに復刻します。さまざまな時代のできごとや荒波を生き抜いてきたSpodeですが、現在は英国ポートメリオンの傘下になっています。世の中にネオクラシカルの流行が現れた時代、上流階級はネオクラシカルに向かっていても、一般家庭はブルー&ホワイトを求めている、一般家庭にブルー&ホワイトを届けようと、1816年に発表した古代ローマを描いた‘ブルーイタリアン’は、200年を超えた現在も世界中で愛されている人気シリーズとなっています。
バーレイ(Burleigh)(正式にはBurgess & Leigh社)
1851年Frederick Burgess Willam Leighによってストークオントレントに創業。豊かな土壌から受け取った材料に、昔ながらの同版転写で描かれた美しい絵柄に今も世界中が魅了されている。工場の老朽化が進んだ際は、チャールズ皇太子財団に保護されながら、職人技術を生かした作品を生み出し続けている。
アジアティックフェザンツは、バーレイが生み出したシリーズのひとつ。高麗キジと牡丹の絵柄は1851年に発表されて以来、現在も世界中にファンが多い、バーレイの代表作。
パラゴン(PARAGON)
バラゴン窯は、エインズレイ窯のジョン・エインズレイの息子のハーバード・エインズレイによって1903年に創業。パラゴンを名乗る以前はスターチャイナ窯として1897年に窯を始めています。上質で煌びやかな美しい器を生み出し、1926年にエリザベス女王が誕生した年から王室に使われるようになり、1933年にメアリー女王から王室御用達(1933年から1934年はRoyal Paragon刻印になっています)を授かっています。時代の波の中で1960年頃からロイヤルドルトン、ロイヤルアルバートに吸収され、1992年にパラゴン窯としての生産を終了し、2000年からウエッジウッド グループとなっています。
ベイカーブラザーズ(Bakers Brothers )(Royal Tudor Wareロイヤルチューダーウエア)
1876年にStaffordshireで創業。陶磁器メーカーとしてBaker兄弟が始めた窯。その後1882年に会社を立ち上げLtdがつく。代表作は’Royal Tudor Ware’と1937年に発表した馬車の絵柄の’Royal Tudor Warecorching Tavern’があり、今なお世界で人気のシリーズです。他にもPrimrose Ware やMay Wareなどのシリーズがあります。どのシリーズも、昔懐かしい英国の風景が描かれ、英国人の心をつかんできました。時代の競争の波に揉まれながら大手に売却したり吸収したりを経て1981年にその歴史の幕を降ろします。
ミントン(MINTON)
MINTON(ミントン)は、イングランドの陶器の町ストーク・オン・トレントで、トーマス・ミントンにより1793年に創業。彫刻師として技術を磨いてきたトーマス・ミントンは、スポードやウェッジウッドの銅板彫刻をしていましたが、自分自身の窯で製造から銅板転写までをしていきたいとの願いからミントン窯がスタートしました。世界にその名を轟かせたミントンですが、創業当時は小さい窯と小さな小屋が出発地点だったそうです。そののち上流階級、王族貴族たちを魅了するセーブルスタイルの上質な陶磁器でその地位を獲得していきます。世界で最も美しいボーンチャイナと呼ばれ、1840年ヴィクトリア女王より賞賛される。そして、1856年から王室御用達となります。
「アフタヌーンティーの代名詞」や「ヴィクトリア女王に愛された陶磁器」の呼び名を持つまでに発展しますが、テーブルウエアだけでなく、実は素晴らしいフィギュアやタイルも製造しています。
そうした世界のミントンですが、時代の変化の中で2015年にウェッジウッド、ロイヤルドルトン、ロイヤルアルバートがフィンランド企業の傘下に入ったことから、同じグループに属していたミントンはその歴史に幕を下ろすことになりました。
メイソンズ(MAISON’S)
1796年にマイルズ・メイソンがロンドンで創業した陶器ブランド。創業当初は陶磁器の輸入業をしていましたが、後に工業を設立し陶器の生産を始めます。1813年に息子のチャールズ・ジェームズ・メイソンが21歳の若さでironstone chinaの特許を取得し、メイソンズは硬くて丈夫な独自の陶器の生産を始めるようになります。美しさと丈夫さを兼ね備えた食器は広く使われるようになり、英国での地位を確立しますが、時代の波の中で、1968年にウェッジウッドグループとなりメイソンズとしての幕を降ろします。
ロイ・カーカム(Kirkham)
英国の陶器の町ストーク・オン・トレントで創業。18世記末にスポードのジョサイア2世が開発した技術を引き継ぎ、薄く堅く焼き上げるファインチャイナを製造しています。高品質な製品と、英国らしさあふれる絵柄で愛され続けているメーカー。中でもピエール・ジョセフ・ルドゥーテが描いたバラを再現したルドゥーテのバラは人気のシリーズ。ピエール・ジョセフ・ルドゥーテは‘花のラファエロ’と呼ばれる画家で、イングリッシュガーデンの主役となっているイングリッシュローズが香るように描かれているプレートやカップは、紅茶文化の英国で英国人のハートをつかんできました。 ロイヤルベントンウエアJohn Steventon & sons Royal Venton
1815年に、ブラウン&スティーベントン社として、ジョン・スティーベントンとパートナーのウィリアム・ブラウンが始めた窯。1923年にウィリアム・ブラウンが引退し、スティーベントンが息子と共に受け継ぎJohn Steventon & sonsとなる。1930年にロイヤルベントンウェアの商号を得て、新しいデザインが次々生み出され人気を博していきます。欧州中の陶器窯がそうだったように、時代の波の中で1936年に歴史の幕を降します。
ロイヤルドルトン(ROYAL DOULTON)
1815年ジョン・ドルトン(John Doulton)がジョン・ワットの共同出資を得て、ストーンウエアを作る工場を設立してロンドンで創業。2代目ヘンリー・ドルトンは最新技術を取り入れ効率を上げながら、排水設備や洗面器、便器などの衛生用品を製品化し、ロンドンの都市化に貢献します。1877年にはバースレムに窯を移し、ボーンチャイナの制作を始め芸術的な作品を生み出していきます。1887年にはヴィクトリア女王から陶磁器界で初めて、ナイトの称号を授かります。さらに1901年にはエドワード7世からはロイヤルの称号を授かります。ナイトとロイヤルを掲げて発展を続け、ミントンとロイヤルアルバートの、英国陶磁器最高の‘ロイヤル’と‘クラウン’の称号を持つロイヤルクラウンダービーを傘下に収め、世界最大の陶磁器メーカーのひとつとなります。その後、2015年ロイヤルコペンハーゲンを所有するフィンランド企業フィスカースに買収され、ウエッジウッドやロイヤルアルバートと共に。WWRDグループホールディングスの一員となります。
KPM ベルリンの正式名称は、KPMベルリン王立磁器製陶所(Konigliche Porzellan Manufaktur)。フリードリヒ大王によって1763年創業。ドイツの主要窯7つのひとつに数えられる人気ある窯。国王自らが選んだバックスタンプはブランデンブルグ選帝侯時代の紋章で、あらゆる分野に王自身が関わり指揮し、マイセンに並ぶ高品質の作品を作り上げ、250年以上の歴史を誇る。
見る資料によって時代が少し違っていたり、内容が違っていたりで、正確な歴史を掘り起こすのは難しいと感じています。
こちらにまとめている内容は、大まかな流れと思っていただきたいことと、SLOW TIMEなりの解釈と見ていただけましたらと思います。どの陶磁器窯も、それぞれの時代を一生懸命生き、努力を重ねてきたことや、陶磁器制作にそれはそれはあふれんばかりの情熱を注いできたことを感じます。その情熱は時代を超えて今なお私たちを魅了し、心をつかんで離さないことで伺い知れます。古い時代の陶磁器は魅力にあふれています。歴史が教科書の中にではなく、体感として感じられるような目には見えない何かがあります。
初めて手にした古い1枚のお皿から、私の生活は一転しました。そのお皿の物語を手探りで探るうち、そこには作られた時の土地のエネルギーが凝縮されていて、歴史そのものだということを知ったのです。
陶磁器は、土地の名前がブランド名になっていますが、まさにその土地の粘土を使い、その土地の水で練り上げられ、その土地の木を薪として使い火を起こして焼かれます。マリーアントワネットがフランス王妃だった時にパリで作られたお皿と知って手に持つ時、そこにはまさにその時代のその場所のエネルギーがそこにあるのです。
お皿を通して歴史を振り返るようになりました。遠い国の出来事が自分に関係のない遠い過去のものではなく、今この瞬間それらを感じられるような気持ちになって、ますます陶磁器の魅力にとりつかれています。
簡単ですが、それぞれの窯の歴史をまとめています。陶磁器のブランドが必死で生き抜いてきたことがうかがい知れると思います。そうしたことを知ってお皿を見ると、胸がきゅんとします。
古いお皿は、人の手が作り出したという証が見えます。絵付けした場所にちょっと触ってしまった後が残っていたり、焼き上げた器を金具で持ち上げた際の金具の跡があったり、ちょっと絵柄がずれていたり。同じお皿でも重さが違ったり、釉薬のかけかたが少しずつ違うことで、艶かげんが1枚ずつ違ったりと、同じお皿といっても個体によって顔が違うことも魅力の一つと感じます。古いお皿には今もなお命が宿っていると感じるのです。
<あいうえお順になっています。>
フランス
エミール・ブルジョワE Bourgeois
南仏マルセイユに窯元を持ち、パリに販売拠点を持ってフランスの上流階級に愛されたブランド。1863年から1918年の50年と言うごく短い時間に高品質で上質な作品を作陶したブランド。
HB&Cie(Hyppolyte-Boulengen&Cie)
1804年にパリ近郊ショワジー・ル・ロア(Choisy le roi)で創業した窯元。ショワジー・ル・ロワ (Choisy Le Roi)でバイヤール3兄弟によって創業後、経営に参加したポリット・ブーランジェが1863年に工場のディレクターとなった後、1878年に社名を変更しH・ブーランジェ(H・Boulenger&Cie)となり最盛期を迎える。その後1920年にクレイユ・エ・モントロー(Creil et Montereau)と合併しHBCM(Hiperolyte Boulanger-Creil-Montereau)社となる。ところが1934年、労働者のストライキによってショワジー・ル・ロワの工場が閉鎖。それを機に、ここでの作陶が終わります。HBCM社として合併先のモントロー工場で作陶は続けられましたが、それも1955年に閉鎖します。
HBCM(Hiperolyte Boulanger-Creil-Montereau)
ショワジー・ル・ロワ (Choisy Le Roi)から始まり、1804年にバイヤール3兄弟によって創業。さかのぼること数年前のこと、バイヤール兄弟が磁器窯シャンティイを当時の所有者だった英国人クリストフ・ポッターから買い取り、ここでの作陶活動をしようとしていた最中の1802年。シャンティイのポッターの部下の筆頭者を始め、職人が丸ごとクレイユに転籍してしまいます。ここでの活動は難しいと判断した兄弟は、新たにショワジー・ル・ロワの地を選びます。
兄弟はここで、当時最新技術だった銅板転写の作陶を始めていきます。19世期後半には他の窯から有能な人物が集められ、窯は最盛期を迎えていきます。この時、経営に参加したイポリット・ブーランジェは1863年に工場のディレクターとなり、1878年に社名を変更しH・ブーランジェ(H・Boulenger&Cie)となっています。現在、市場で見ることのできるものは、量産ができるようになった1800年半ばから閉窯の1900年前半のものが多いようです。イポリット・ブーランジェ亡き後は彼の2人の息子が引き継ぎます。1895年にはクレイユ工場は火事によって閉鎖し、経営が困難になっていたクレイユモントローとモントロー工場を買収する形で1920年に合併、HBCM(Hiperolyte Boulanger-Creil-Montereau)社となります。その頃、メトロの壁面に使用されるタイル製造で栄えます。ところが1934年、労働者のストライキによってショワジー・ル・ロワの工場が閉鎖し、それを機にショワジー・ル・ロワでの作陶は終わります。HBCM社として合併先のモントロー工場で作陶は続けられましたが、それも1955年に閉鎖し歴史に幕を降ろします。
クレイユ・エ・モントロー(CREIL ET MONTEREAU)
クレイユとモントローのふたつの窯がひとつになって生まれた陶磁器ブランドです。
モントロー窯の創業は1749年。フランソワ・マゾワによってモントロー陶器工場が作られ、ファイアンス・フィンを発展させていきます。モントローでは陶器作りに適した白い粘度が採れたことから、クレイユにも材料を提供していました。工場ができる前の最初の窯は1719年頃に始まっています。オーナーや生産様式の変化と時代を生き抜きながら、1819年に作陶ではライバル的存在だったクレイユと合併し、クレイユ・エ・モントローとして共同制作を始めます。
一方、クレイユ窯の創業は1797年頃。英国人起業家のクリストフ・ポッターが経営に加わり、英国ではすでに発明されていた、陶器や磁器に印刷をする技術を、フランスではクレイユとジョワジー・ル・ロワが初めて導入し、窯は大きく発展します。この頃、新古典主義の作品が次々作られていきます。さらにその後新たな技術者が加わりながら発展し、オーナーの交代も経ながら(1840年から1874年までは当時合併していたオーナー名の‘Lebeuf Milliet et Cie’の刻印がされています。)1819年頃にモントロー工場を買収した形でクレイユ・エ・モントローとなります。
クレイユ・エ・モントローの作陶は優れた銅板転写で、まるでキャンパスに絵を描くような色鮮やかな陶器が特徴でした。古典主義、シノワズリ、アールヌーボーと時代とともに多くの作品を生み出してきました。フランスを代表する古窯として発展を続けてきましたが、1895年クレイユの工場が火事になり工場が閉鎖。その後もクレイユ・エ・モントローの名前で1920年まで制作を続けますが、その後ジョワジー・ル・ロワに吸収され、HBCM(H・ブーランジェー・クレイユ・モントロー)として製作が続けられました。しかし、さまざまな時代の波を乗り越えてきたものの1955年その歴史に幕を降しました。
サラン-レ-バン(SALINS-LES-BAINS)
サラン-レ-バン(SALINS-LES-BAINS)窯は、スイスとの国境に近いフランス東部のジュラ県、サラン-レ-バン(SALINS-LES-BAINS)で、1857年にファイナンスリーの製造所として創業。サラン-レ-パン(SALINS-LES-BAINS)は、古くから塩の製造でも知られる土地です。1912年にロンシャンディレクターの息子がサラン窯のディレクターとなり、洗練された作陶をしていきます。そして、そのまま所有者になり精力的に制作を続けていきますが、時代の変化の波のなかで1968年にサルグミンヌに吸収されていきます。一般向けの製造は1988年に、高級品の製造は1998年に終了しています。
サルグミンヌ(SARREGUEMINES)
1784年にニコラス・アンリ・ヤコビとそのパートナーによって、ドイツとの国境に隣接するサルグミンヌで創業。しかし経営はうまく行かず、19世期に、工場はドイツ人のポール・ウィッチシュナイザー(Paul Utzschneider)に引き継がれます。この頃の刻印はF&U (Fabry&Utzschneider)。ビジネスに長けていたポールはサルグミンヌを国際博覧会で世界に紹介し、彼の顧客はナポレオンやブルボン王朝まで到るようになります。工場の経営は順調に進み、1830年位はヴィレロイ&ボッホと資本協力し、市場を分け合うほどに成長します。そしてそれまでの薪を使っての窯焼き(薪オーブン)を蒸気運転(石炭オーブン)に設備を整え生産力も向上していきます。
ところが、1870年の普仏戦後サルグミンヌがフランス領からドイツ領に変わり、完成品をフランスに運ぶために陶器に膨大な輸出税がかかるようになったことと、サルグミンヌとしてのフランス籍を守るため、1876年にフランスブルゴーニュ地方の小さな町ディゴワンにサルグミンヌ窯を移します。
この時、ドイツ側にはUtzschneider & Cie(U&C Sarreguemines)を置き、(ドイツ側はUtzschneiderの娘婿が経営を引き継ぎ刻印はU&C(U&Cieに))、フランス側は当時すでに陶器制作をしていたディゴワン(Digoin)と合併しDigoin &Sarregueminesと、ドイツとフランスと2つの会社に分割します。
ディゴワンでは、Digoin、Sarreguemines、Digoin &Sarregueminesの3つの刻印が当初使われていましたが、その後会社名をDigoin &Sarregueminesに変更し、1881年から総称をFaienceries de Sarreguemines、Digoin et Vitry-le-Francois(ヴィトリールフランソワ) と呼ぶようになります。ディゴワンでは、ディゴワン&サルグミンヌとして100年以上に渡り、数々の陶器生産を続けてきました。
第一次大戦のドイツの敗戦によりサルグミンヌ製陶工場は再びフランス領に戻るのですが、その後は経営不振により1942年から3年間、ヴィレロイ&ボッホに経営が委託され、さらに時代の流れに逆らえず、1978年にリュネヴィル・バドンビレー・サンクレマングループに買収され、この年で食器の生産を終えています。その後はタイル製造に専念してきましたが、2002年に株主となった従業員に製造が引き継がれて、2007年に破産宣告と共にフランスを代表するディゴワン・サルグミンヌとしての古窯は200年を越える歴史の幕を降しました。
サンタマン(Saint Amand)
フランス北部、ベルギーに近いノール県のサンタマン・レゾー(Saint-Amand-les-Eaux)に、ニコラス・デムウティエールよって1705年に創業。スカーぺ川の粘土を採取、近くの森から窯のために木材を得て、完成した陶器はスカーぺ川で運ぶことができると言う陶器制作に恵まれた土地で、ファイアンス焼きを始めます。花や動物の絵柄や伝統的なブルー&ホワイトの作品が作られていきました。その後、さまざまなオーナー遍歴を繰り返し、またフランス革命によって工場が閉鎖するなど時代の波をくぐり抜けながら、1928年ムーラン・デ・ル・アマージュと名前を変更。1944年にはさらに、ムーランデルーと名前を変更すします。このとき会社は国内に5カ所展開していましたが、時代の変化に応じながら1952年からひとつずつ工場を閉鎖し、1962年には最後の工場を閉鎖してその歴史に幕を降しました。様々な遍歴を繰り返してきたためさまざまな作風と多くの刻印が存在します。現在では作陶の起源である地名の名前を取って総称してサンタマン=レゾーの陶器と呼ばれています。現在のアンティーク市場では1880年以降の作品が主となっています。
ジアン(GIEN)
正式名称は’Faiencerie de Gien’と。この名前が物語るようにGienはファイアンス焼きの陶器ブランドとなります。
ファイアンス焼きとは繊細な淡黄色の土に錫秞(しゃくゆう)をかけて焼く陶器のこと。陶器を焼く前に使われる釉薬に酸化スズを加えることで絵付に適するようになり、色鮮やかな陶器が生まれていく。
ジアンはパリの南にある緑豊かな小さな町。ロワール川が流れ、豊かな土壌と温暖な気候に恵まれたジアンで、1821年ジアン窯が創業する。創業者は英国人実業家のトマス・エドム・フルムで、英国の製陶技術を生かして始まりました。原料となる粘土はロワール川から採取し、窯の燃料となる材木は近くのオルレアンの森から得て、完成した陶器はロワール川で運搬すると言うように、窯を開くにあたってそこにすべてが揃っていた場所で始まり、現在も活動中。公式HP https://gienfrance.jp
ショワジー・ル・ロワ(CHOISY LE ROI)(Choisy Le Roi)
1804年にバイヤール3兄弟によって創業。さかのぼること数年前のこと、バイヤール兄弟が磁器窯シャンティイを当時の所有者だった英国人クリストフ・ポッターから買い取り、ここでの作陶活動をしようとしていた最中の1802年。シャンティイのポッターの部下の筆頭者を始め、職人が丸ごとクレイユに転籍してしまいます。ここでの活動は難しいと判断した兄弟は、新たにショワジー・ル・ロワの地を選びます。
兄弟はここで、当時最新技術だった銅板転写の作陶を始めていきます。19世期後半には他の窯から有能な人物が集められ、窯は最盛期を迎えていきます。この時、経営に参加したイポリット・ブーランジェは1863年に工場のディレクターとなり、1878年に社名を変更しH・ブーランジェ(H・Boulenger&Cie)となっています。現在、市場で見ることのできるものは、量産ができるようになった1800年半ばから閉窯の1900年前半のものが多いようです。イポリット・ブーランジェ亡き後は彼の2人の息子が引き継ぎます。1902年にはクレイユは火事によって工場が閉鎖し、経営が困難になっていたクレイユモントローとモントロー工場を買収する形で合併し、HBCM(Hiperolyte Boulanger-Creil-Montereau)社となります。その頃、メトロの壁面に使用されるタイル製造で栄えます。ところが1934年、労働者のストライキによってショワジー・ル・ロワ工場は閉鎖し、それを機にここでの作陶が終わります。HBCM社として合併先のモントロー工場で作陶は続けられましたが、1955年に閉鎖し歴史に幕を降ろします。
バドンヴィレ(BADONVILLER)
バドンヴィレの歴史は、フェナル一家がペクソンヌで窯を始めたところから始まります。ペクソンヌ窯はリュネヴィル、ニダーヴィレー、サンクレモン、バドンヴィレーなど著名な窯がある場所で、陶磁器作りに向いた土地でした。ペクソンヌ窯は1720年頃から始まった古窯で、1836年からニコラ・フェナルが正式オーナーとなります。ニコラ亡き後は息子と甥たちが引き継ぎFenal Frères(FF)の刻印が使われています。そこからペクソンヌは大きく成長していき、近隣の陶磁器製造の窯の職人たちもペクソンヌに移り、さらに素晴らしい作品を生み出して、ペクソンヌ フェナル兄弟(PEXONNE FENAL Freres)として成功を収めます。その後、1897年にペクソンヌ フェナル兄弟の中の一人だった甥のテオフィル・フェナル(Thèophile Fenal)は家族とうまく行かず、ペクソンヌ窯から分鎌する形でバドンヴィレーに独立し、1898年バドンヴィレ工場を作ります。これがバドンヴィレの始まりです。刻印はTF(Thèophile Fenal)となり、銅板からの写絵のような特徴的なペイントやエアブラシの装飾技法などにチャレンジし、すぐに300名の従業員を雇うまでに成長します。1905年のテオフィル亡き後は息子のエドゥワルドが引き継ぎ、すぐに従業員1000名を超えるまでに拡大していきます。アールヌーヴォーテーブル食器74ピースセットなどの大作を作るなど、バドンヴィレの栄光の時代を飾ります。1920年にエドゥワルドはリュネヴィル・サン=クレモン窯の指揮もするようになり、刻印に「KG」が刻まれます。その後第二次世界大戦後では縮小したものの、戦後はエドゥワルドの息子のジルベートが後を継ぎ、さらにヴァドンヴィレは発展していきます。1950年頃のフェナルグループの窯は、フランスの30%を占めていたそうです。1963年にはバドンヴィレ窯とリュネヴィル・サン=クレモン窯をひとつにして生産を始め(合併後の刻印はBadonvillerに統一されています)、1980年にはフェナルグループはサルグミンヌ窯とも合併し(Sarreguemines 社と合併後は刻印をLunevillーSt・Clementにしています)、生産を続けていきます。しかし1990年にバドンヴィレ窯はサン=クレモン窯のみを残して歴史に幕を降ろします。バドンヴィレーは新興窯ながら特に1900年後半のフランスで地位を確立した窯です。
ペクソンヌ(PEXONNE)
1719年、ペクソンヌにニコラス・フェナルが窯を始めます。近隣諸国との戦争が続いていた時代、金属類の不足から、ルイ14世は銀食器の使用禁止を命じたため、‘銀食器に代わるものをファイアンスで作りなさい’とロレーヌ地方の公爵がペクソンヌ村に窯を作らせたのが始まりです。1836年からニコラスが正式オーナーとなり、ニコラス亡き後は息子と甥たちが引き継ぎ(バックスタンプはFenal frères((F F))大きく成長していきます。ペクソンヌはリュネヴィル、ニダーヴィレー、サンクレモン、バドンヴィレーなど著名な窯がある場所でしたが、それらで活躍していた職人たちがペクソンヌに移ったことで、窯は大いに盛り上がります。そこで、ペクソンヌ フェナル兄弟(PEXONNE FENAL Freres)として成功を収めます。その後甥の一人のテオフィル・フェナルがバドンヴィレーに窯を開いて分窯。新しい手法を展開していくバドンヴィレーに注目が集まるようになり、次第にバドンヴィレーが優勢になっていきペクソンヌ窯は終わりを迎えることになります。
リュネヴィル(Luneville)
ロレーヌ地方のムルト・エ・モゼル県にあるリュネヴィル(古くは女神ディアーナを信仰する‘月Luna’と名前が入ったLunae-villeが土地の呼び名の始まり)で、近郊のサンクレマンで採れる粘土を元に、1728年にジャック・ジャンブレットがリュネヴィルに最初の陶器工場を設立し、リュネヴィル焼きの制作を始めます。1758年にはサンクレマンに第2工場を設立します。当初は上流階級向けの高級な食器を生産し、1749年にはロレーヌ公の領主御用達になっています。ルイ14世の時代、戦争のための資金調達のためシルバー製の食器製造が国王によって禁止されていた1700年〜1800年に、ロレーヌ公の命によってファイアンス焼きの食器の製造が始まっています。
ジャック亡き後、ドイツ出身のケラー(Kellen)ファミリーと友人ゲラン(Guerin) ファミリーが経営を引き継ぎ、刻印はLuneville K&Gとなります。
ここから貴族のための陶器から中流階級のための食器も手がけていきます。マリーアントワネットはリュネヴィルの食器を愛し、リュネヴィルの保護もしています。小トリアノンの庭に飾られていた食器は1500とも2000とも言われています。チューリップやバラなどの花々や、鳥や動物などが描かれた温かく優しい絵柄をはじめ、1800年後半にはシノワズリやアール・ヌーヴォーなどの流行のデザインも取り入れられ、フランス国内のみならず、ヨーロッパ中に輸出されるようになります。
それでも世界の変化とともに、1922年にはバドンヴィレが工場を買収し合併します。さらに1979年にはサルグミンヌと合併しています(この時の刻印はLuneville-St Clement)。
その後、1981年にリュネヴィル窯は生産を停止。サンクレマン工場は1999年に生産を停止、その歴史に幕を降すことになります。
ロンウィー(LONGWY)
北フランスロレーヌ地方のロンウィに1798年創業。シャルル・レ・ニエが古い修道院の中に作陶の窯を作ったのが始まりです。1810年のナポレオン戦争時、ドイツ軍による市内包囲によって工場は活動停止し困窮しますが、ルクセンブルクのヴィレロイ&ボッホ創始者の親戚にあたるジャン・アントワーヌ・ド・ノトームが窯を買い取り、経営を引き継ぎます。1800年半ばにはロンウィーエナメルと呼ばれるエナメル陶器の生産を始め、陶器ブランドとしてその地位を獲得。1900年には初期アールデコ陶器を制作したりと精力的に生産を続けています。
ドイツ
KPM ベルリン
正式名称は、KPMベルリン王立磁器製陶所(Konigliche Porzellan Manufaktur)。フリードリヒ大王によって1763年創業。ドイツの主要窯7つのひとつに数えられる人気ある窯。国王自らが選んだバックスタンプはブランデンブルグ選帝侯時代の紋章で、あらゆる分野に王自身が関わり指揮し、マイセンに並ぶ高品質の作品を作り上げ、250年以上の歴史を誇る。
ビレロイ&ボッホ(VILLEROY&BOCH)
1748年フランソワ・ボッホによって、フランスのロレーヌ地方に創業。その後ルクセンブルグにも工場を設立。ハプスブルグ家の援助を受け王室御用達の窯として発展する。その後1836年に陶器制作ではライバルでもあったビレロイ家と合併し、ドイツに本社を構えてビレロイ&ボッホとなる。2つの力を合わせていち早く制作の工業化を始め、マイセン、ロイヤルコペンハーゲンに並ぶ世界三大陶磁器の会社となる。
現在はメトラッハに本社を持つドイツの陶磁器会社。
イギリス
アダムズ(ADAMS)
1657年にジョン・アダムスがThe Adams familyとして家族でStaffordshireのバースレムに窯を起こしたのが始まり。代々続く陶芸づくりの家に生まれたウィリアム・アダムスもまた兄弟と同じく、家業に携わっていきます。のちにウィリアムが引き継ぎ、18世紀の初めには銅板プリント転写技術を確立し、英国らしさ溢れる食器を生み出していきます。この頃の作品はWilliam Adamsと呼ばれているようです。
17世期から始まり、代々受け継がれてきたADAMSは、英国の陶器づくりの世界でもかなり古窯です。
確立した転写技術は外部にもれないよう、二人の職人のみによって極秘で行なわれていたそうです。
ウィリアムからさらに息子たちに引き継がれて、しっかりと製造技術を守りながら先祖11代まで受け継がれてきましたが、さまざまな窯が発展していく中で、競争が激しくなっていたのだろうとも想像します。
時代の波から逆えず、1966年にウェッジウッド(Wegewood)グループに吸収されます。
そこからの作品はウエッジウッドらしい上品なムードを醸し出すようになったと感じます。
それ以前のADAMSは素朴さが漂っているように感じます。
ウェッジウッド(Wedgwood)
1759年にジョサイア・ウェッジウッドがStaffordshierに創業した英国の陶磁器メーカー。努力を重ねた開発の末生まれたエネメルを用いたクリーム色の陶器は絶賛され、1765年には「クイーンズウェア(女王の陶器、Queen's Ware)」という名称を与えられる。開発拡大とともに世界的な輸入も始まりウェッジウッドの名が世界に轟いていくが、時代の波の中で買収拡大をしながら、2015年フィンランド企業フィスカースに買収され、ロイヤルドルトン、ロイヤルアルバートと共にWWRDグループホールディングスの一員となる。
ウッド&サンズ(Wood&Sons)
1865年、Absalom Woodとその息子たちと創業。1910年に会社設立と世代交代をして多くのテーブルウエアを製造してきました。中流階級向けの老舗陶磁器メーカーとして英国中の家庭でよく目にするブランドです。銅板転写によりブルー&ホワイトで英国のカントリーサイドが描かれる作品が得意です。残念ながら時代の変化の中で1995年に閉窯しました。
エインズレイ (Aynsley)
1775年ジョン・エインズレイ によって創業。2代目の時代にティーセットに情熱が注がれ、 3代目の時代にはスポードが開発したファイン・ボーンチャイナの技術を取り入れ、高品質な製品を生み出していきます。 ヴィクトリア女王やエリザベス2世など英国王室に愛され、その地位を獲得しています。華やかな花々が描かれ、金彩を施したティーセットは今も世界中にファンを持っています。現在は80か国に輸出されている英国の古窯になっています。
エノク・ウエッジウッド(ENOCH WEDGWOOD)の始まりは1834年。タンストール(Tunstall)で活動していたユニコーン窯(Unicorn Pottery)は、Swan Bank Potteryほか2つの窯と合併吸収しながら活動を続けてきたが、1859年にはウェッジウッドの創業者のジョサイア・ウェッジウッドの遠い親戚だったエノク ・ウェッジウッドが事業を引継ぎ、Wedgwood & Coと名前を変えます。1900年にはWedgwood & Co Ltdとなり、Imperial Porcelain、Royal Stone China、Wacol Ware、Wacol Imperial, Royal Tunstallなどで陶器の製造をします。1965年にはWedgwood & Co LtdとPinnox Potteryが合併し、Enoch Wedgwood (Tunstall) Ltd となります。英国の陶器窯はフランスと同じく、吸収されながら成長し今に至っていまが、1980年にはウエッジウッド・グループに吸収されます。
ジョンソンブラザーズ(Jonson Brothers)
イギリス ストークオントレントで1883年創業の食器ブランド。オリジナルの4人の「ジョンソンブラザーズ」は、アルフレッド、フレデリック、ヘンリー、ロバート。彼らの父は、陶芸家のアルフレッド・ミーキンの娘と結婚後、陶器の生産を始めます。創業当初はホワイトグラナイト「白い花崗岩」と呼ばれる耐久性のある陶器を制作。その後、高級陶器の特徴を持ちながら、鉄石製品の耐久性を備えた「半磁器」と呼ばれる陶器を開発し、高い人気を得ます。輸出業も波に乗り成長しますが、第二次大戦で工場は停止。戦後は設備を整え再建を目指します。ジョンソンブラザーズは、英国経済への貢献により、クイーンエリザベス2世とクイーンマザーからロイヤルワラントを受賞しています。1890年代から1960年代にかけて、米国に多く輸出された食器を製造した最も成功したスタッフォードシャー陶器として地位を確立。また衛生設備がなかった時代に、バスルームセラミックの重要なメーカーとして開発に力を注ぎ、衛生設備を整えることにも貢献しています。しかしながらこうした2度の受賞も、1960年半ばには競争の激化が始まり、時代の波の中でウェッジウッドグループに吸収されます。そこから1968年から2015年まではウェッジウッドでの製陶活動があったものの、2015年にウェッジウッドグループがフィスカースに買収された後、ジョンソンブラザーズは132年間の歴史の幕を降します。
スポード(Spord)
1770年陶芸家ジョサイア・スポードがストーク・オン・トレントに陶芸工業を開設。実際にはジョサイア・スポード幼少期から小さな陶器工房で丁稚奉公を始め、16歳の時、陶器の世界に身を埋める覚悟をします。就職した陶器工房でのちのウエッジウッドの創始者のジョサイア・ウェッジウッドが共同経営者として加わり、彼からも影響を受けていきます。いくつかの窯を歩きながら修行を重ね、1770年ごろから自らが焼いた陶器にSpodeの名前を入れるようになります。そこからSpode窯は1770年創業と呼ばれるようになっています。研究熱心なジョサイア・スポードは銅板転写技術による絵付け技術を開発し、さらにボーンチャイナを完成させるなど開発に力を注ぎながら、陶器と磁器の両方の長所を持つストーンウエアを完成させます。これにより1806年ジョージ4世より英国王室御用達としてロイヤル・ウォラントの称号を授かります。1833年には買収によってオーナーが変わリ、販路拡大に成功して英国を代表するブランドのひとつとなります。1843年位はボーンチャイナを超えるファインチャイナを完成させます。1847年に長年ともに共同経営をしてきたコープランド家がW・T・コープランドとして正式オーナーとなります。1863年にはコープランドの4人の息子が加わり、W・T・Copeland & sonsと改名。1970年にはコープラントが窯の権利を売却したことで、窯の名前はSpode.Ltdに復刻します。さまざまな時代のできごとや荒波を生き抜いてきたSpodeですが、現在は英国ポートメリオンの傘下になっています。世の中にネオクラシカルの流行が現れた時代、上流階級はネオクラシカルに向かっていても、一般家庭はブルー&ホワイトを求めている、一般家庭にブルー&ホワイトを届けようと、1816年に発表した古代ローマを描いた‘ブルーイタリアン’は、200年を超えた現在も世界中で愛されている人気シリーズとなっています。
バーレイ(Burleigh)(正式にはBurgess & Leigh社)
1851年Frederick Burgess Willam Leighによってストークオントレントに創業。豊かな土壌から受け取った材料に、昔ながらの同版転写で描かれた美しい絵柄に今も世界中が魅了されている。工場の老朽化が進んだ際は、チャールズ皇太子財団に保護されながら、職人技術を生かした作品を生み出し続けている。
アジアティックフェザンツは、バーレイが生み出したシリーズのひとつ。高麗キジと牡丹の絵柄は1851年に発表されて以来、現在も世界中にファンが多い、バーレイの代表作。
パラゴン(PARAGON)
バラゴン窯は、エインズレイ窯のジョン・エインズレイの息子のハーバード・エインズレイによって1903年に創業。パラゴンを名乗る以前はスターチャイナ窯として1897年に窯を始めています。上質で煌びやかな美しい器を生み出し、1926年にエリザベス女王が誕生した年から王室に使われるようになり、1933年にメアリー女王から王室御用達(1933年から1934年はRoyal Paragon刻印になっています)を授かっています。時代の波の中で1960年頃からロイヤルドルトン、ロイヤルアルバートに吸収され、1992年にパラゴン窯としての生産を終了し、2000年からウエッジウッド グループとなっています。
ベイカーブラザーズ(Bakers Brothers )(Royal Tudor Wareロイヤルチューダーウエア)
1876年にStaffordshireで創業。陶磁器メーカーとしてBaker兄弟が始めた窯。その後1882年に会社を立ち上げLtdがつく。代表作は’Royal Tudor Ware’と1937年に発表した馬車の絵柄の’Royal Tudor Warecorching Tavern’があり、今なお世界で人気のシリーズです。他にもPrimrose Ware やMay Wareなどのシリーズがあります。どのシリーズも、昔懐かしい英国の風景が描かれ、英国人の心をつかんできました。時代の競争の波に揉まれながら大手に売却したり吸収したりを経て1981年にその歴史の幕を降ろします。
ミントン(MINTON)
MINTON(ミントン)は、イングランドの陶器の町ストーク・オン・トレントで、トーマス・ミントンにより1793年に創業。彫刻師として技術を磨いてきたトーマス・ミントンは、スポードやウェッジウッドの銅板彫刻をしていましたが、自分自身の窯で製造から銅板転写までをしていきたいとの願いからミントン窯がスタートしました。世界にその名を轟かせたミントンですが、創業当時は小さい窯と小さな小屋が出発地点だったそうです。そののち上流階級、王族貴族たちを魅了するセーブルスタイルの上質な陶磁器でその地位を獲得していきます。世界で最も美しいボーンチャイナと呼ばれ、1840年ヴィクトリア女王より賞賛される。そして、1856年から王室御用達となります。
「アフタヌーンティーの代名詞」や「ヴィクトリア女王に愛された陶磁器」の呼び名を持つまでに発展しますが、テーブルウエアだけでなく、実は素晴らしいフィギュアやタイルも製造しています。
そうした世界のミントンですが、時代の変化の中で2015年にウェッジウッド、ロイヤルドルトン、ロイヤルアルバートがフィンランド企業の傘下に入ったことから、同じグループに属していたミントンはその歴史に幕を下ろすことになりました。
メイソンズ(MAISON’S)
1796年にマイルズ・メイソンがロンドンで創業した陶器ブランド。創業当初は陶磁器の輸入業をしていましたが、後に工業を設立し陶器の生産を始めます。1813年に息子のチャールズ・ジェームズ・メイソンが21歳の若さでironstone chinaの特許を取得し、メイソンズは硬くて丈夫な独自の陶器の生産を始めるようになります。美しさと丈夫さを兼ね備えた食器は広く使われるようになり、英国での地位を確立しますが、時代の波の中で、1968年にウェッジウッドグループとなりメイソンズとしての幕を降ろします。
ロイ・カーカム(Kirkham)
英国の陶器の町ストーク・オン・トレントで創業。18世記末にスポードのジョサイア2世が開発した技術を引き継ぎ、薄く堅く焼き上げるファインチャイナを製造しています。高品質な製品と、英国らしさあふれる絵柄で愛され続けているメーカー。中でもピエール・ジョセフ・ルドゥーテが描いたバラを再現したルドゥーテのバラは人気のシリーズ。ピエール・ジョセフ・ルドゥーテは‘花のラファエロ’と呼ばれる画家で、イングリッシュガーデンの主役となっているイングリッシュローズが香るように描かれているプレートやカップは、紅茶文化の英国で英国人のハートをつかんできました。 ロイヤルベントンウエアJohn Steventon & sons Royal Venton
1815年に、ブラウン&スティーベントン社として、ジョン・スティーベントンとパートナーのウィリアム・ブラウンが始めた窯。1923年にウィリアム・ブラウンが引退し、スティーベントンが息子と共に受け継ぎJohn Steventon & sonsとなる。1930年にロイヤルベントンウェアの商号を得て、新しいデザインが次々生み出され人気を博していきます。欧州中の陶器窯がそうだったように、時代の波の中で1936年に歴史の幕を降します。
ロイヤルドルトン(ROYAL DOULTON)
1815年ジョン・ドルトン(John Doulton)がジョン・ワットの共同出資を得て、ストーンウエアを作る工場を設立してロンドンで創業。2代目ヘンリー・ドルトンは最新技術を取り入れ効率を上げながら、排水設備や洗面器、便器などの衛生用品を製品化し、ロンドンの都市化に貢献します。1877年にはバースレムに窯を移し、ボーンチャイナの制作を始め芸術的な作品を生み出していきます。1887年にはヴィクトリア女王から陶磁器界で初めて、ナイトの称号を授かります。さらに1901年にはエドワード7世からはロイヤルの称号を授かります。ナイトとロイヤルを掲げて発展を続け、ミントンとロイヤルアルバートの、英国陶磁器最高の‘ロイヤル’と‘クラウン’の称号を持つロイヤルクラウンダービーを傘下に収め、世界最大の陶磁器メーカーのひとつとなります。その後、2015年ロイヤルコペンハーゲンを所有するフィンランド企業フィスカースに買収され、ウエッジウッドやロイヤルアルバートと共に。WWRDグループホールディングスの一員となります。
KPM ベルリンの正式名称は、KPMベルリン王立磁器製陶所(Konigliche Porzellan Manufaktur)。フリードリヒ大王によって1763年創業。ドイツの主要窯7つのひとつに数えられる人気ある窯。国王自らが選んだバックスタンプはブランデンブルグ選帝侯時代の紋章で、あらゆる分野に王自身が関わり指揮し、マイセンに並ぶ高品質の作品を作り上げ、250年以上の歴史を誇る。